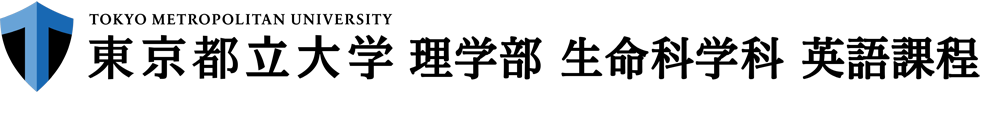グローバルコミュニケーションキャンプ 参加者インタビュー
今年度もグローバルコミュニケーションキャンプが実施され、5名の学生らが授業提携をしているSUNY(ニューヨーク州立大学オネオンタ校)を訪問しました。帰国後、インタビュー座談会を開き、現地滞在中の様子を聞いてみました。(プライバシー保護のため、学生はイニシャル表記です。Y.Mさん、F.Sさん、N.Kさん、T.Tさん)
<Q1>今回、グローバルコミュニケーションキャンプに参加した動機は何ですか?
-F.S:入学当初より留学に興味はあったのですが、これまで実行できずに悔しさを感じていたところ、このキャンプの存在を知りました。
-Y.M:私も在学中に一度は海外の大学という違った環境に行ってみたいと思っていましたので。
-N.K:英語を使ったコミュニケーションにかねてから関心があったので、自分の研究を英語でプレゼンテーションするのは貴重な機会だと思いました。
<Q2>キャンプの一番の目的は自分の研究を英語で発表することですね。渡航前はプレゼンテーション練習を重ねたと聞いています。苦心・工夫した点を教えてください。
-N.K:私は専門用語を英語にしたり、学名を使ったりするのが慣れずに大変でした。スライドは日本語で発表する場合より文字数が多くなりがちだったので、それらを減らす分、レイアウトの工夫で見せるなどしました。初めて研究を聞く人にも分かりやすいようにワーキングモデルを簡素な模式図を使って表したりしました。
-F.S:専門用語を英語に・・・はまさに同感です。数学的な要素を織り交ぜながら説明する部分で、普段はあまり使わない数学英語を用いたのでそれが大変でした。
-T.T:私はポスター作成の経験が無かったため、特に苦戦しました。(引率の)淺田先生から「グラフや図を中心にとして文章説明は最小限」「読み手に伝わりやすい配色、配置」などのご指導をいただきました。それらはとても難しかったのですが、要約・まとめの過程で自分の研究をあらためて振り返ることができ、目的/仮説/考察において私の考えていたことを整理することが出来ました。
-F.S:私も説明練習を繰り返す中で無駄なところを省いていくことが出来ました。ポスター作成も図や文字の大きさ・バランスについて、先生やメンバーがアドバイスをしてくれたので、見やすいものに完成させることが出来ました。
-Y.M:プレゼン練習において、質問に対してとっさに英語で答えることが出来ないことに気づきました。そのため質問されそうなことに対するイラストを挿入し、拙い英語でも伝わるよう工夫をしました。
<Q3>SUNYで体験した授業について聞かせてください。本学にない授業でしたら是非聞かせてください。
-N.K:興味のある爬虫両棲類学の授業に出ました。世界各地のカメの種類と生態についてでした。都立大にはそのような特定の生物種に絞って深く取り扱うということはしないので新鮮な体験でした。担当の先生にはさらにわがままを聞いていただいて、現地の大学周辺で採集した両棲類の標本を見せていただきました。日本にはいないような不思議な生態の両棲類がおり、現地でしか味わえない感動を味わえました。シンポジウムではその先生の研究室の院生がカエルの卵のクラスタリングについて発表したのですが、そのテーマも自分にとっては刺激的なもので、発表の後、その院生とコミュニケーションを取りました。実験条件の再考につながる良いアドバイスをもらい、連絡先も交換し、これからも継続的に連絡を取ろうとなり・・・。自分の研究の人脈の幅が大きく広がった旅になった。
-F.S:私が特に印象に残っているのは“INTRO TO CRIMINAL JUSTICE”、“STAGE MAKEUP”の授業と人類学研究室の訪問です。“INTRO TO CRIMINAL JUSTICE”はアメリカの警察についての授業で、個人的にとても興味のある分野なので歴史も含め学ぶことができて嬉しかったです。日本でのこのような授業は受けたことはなく、アメリカ人視点の意見を含んだ授業は聞いていて新鮮でした。“STAGE MAKEUP”は恐らく学内にある舞台の楽屋を使った授業でした。舞台の楽屋を使って実際にメイクをする授業があること自体にとても驚きました。人類学研究室の訪問は本当に感銘を受けました。もともと高校時代に学びたい分野の候補に人類学があったので、授業の風景をみたり展示物が置いてある教室をみてまわったりするのがとても楽しかったです。
-T.T:私は調理実習に参加しました。英語で書かれたレシピを渡されて、なんとか教授の言っていることを理解して料理を行いました。向こうの授業の雰囲気は都立大の講義よりも学生と教授の距離感が近く、学生に積極的に発言や考える機会を与える形式のものが多いと感じました。
-Y.M:私は日本語の授業に参加しました。日本語で自己紹介をしたり、学生さんが考えてきた日本語での質問に答えたりしました。世界共通語である英語をすでに話せている中、難しいといわれている日本語を熱心に勉強している学生の様子を見て、私も英語の習得にむけてさらに勉強しようというモチベーションを得られました。
<Q4>授業、研究室の様子・雰囲気はどんなでしたか? また訪問した際の英語コミュニケーションはどうでしたか?
-N.K:現地の学生は皆、単位のために勉強しているというより、自分の興味のおもむくままに勉強しているという感じで、挙手も自然と上がっていました。
-F.S:授業によってはしっかり手を挙げて発表するというよりも学生たちの軽いつぶやきによってディスカッションが構成されているものもありました。気軽に発言できる雰囲気がとても素敵だと感じました。全体的に授業のわからないところはすぐに質問する学生が日本よりも多い印象でした。
-Y.M:コミュニケーションに関しては、オネオンタの先生方、学生がゆっくりはっきり話してくださり、英語がつたない私に向けてたくさん歩み寄ってくださいました。(一同、同感)
-T.T:私がより流暢に話すことが出来ればより楽しめた、と。次回会うために英語の勉強を再開しようとモチベーションになる良いきっかけになりました。
-F.S:最初のうち、話す際に文法にこだわってしまう部分があったのですが、あまり深刻に考えずに話してみると意外と単語が出てきたので途中からは恐れずに話そうと切り替えることができました。会話は形式にこだわりすぎるよりも楽しむことがまずは大切だと再認識しました。
<Q5>宿泊した学生寮ではどのように過ごしたのですか? 食事はどうしていたのですか?
-T.T:ベッドが大きくとても快適に生活することが出来ました。
-N.K:ラウンジがあったのでタイミングが合えば仲間とそこでご飯を食べたり、1日の出来事について意見を交わしたりできました。
-F.S:朝ご飯は主に持参していた白米を電子レンジで温めて食べていました。お昼は授業が前後にあったので学内のカフェテリア等に行きました。注文が少し大変でしたが、アジアンフードを含むたくさんのジャンルの料理がありとてもおいしかったです。ボトルさえ持っていれば水はどこでも補給できて、それはとても驚きました。
<Q6>SUNYキャンパスで授業の他に経験出来たこと、さらには大学の外で経験出来たことはありますか?
-N.K: オネオンタ校のみなさんがとてもあたたかく、たくさんもてなしをしてくださいました。何かわからないことがあっても学生さんに聞けば誰でも親切に教えてくれるし、店員さんも笑顔で「東京から来てるの?」と聞いてくれました。大学にいて人に対して不快感をいだくことが一度もなく、むしろ毎日あたたかい気持ちでいっぱいになった。アメリカの国民性に良い意味でカルチャーショックを受けました。
-Y.M:私は現地の保育園で交流したことが印象に残っています。日本の紙芝居を読み、おにぎりを実際に作り、折り紙で作ったハートや猫をプレゼントしました。海外のことを学ぶだけではなく、日本のことを海外に伝える体験もできました。
-F.S:やはり実際に歩いてみることで感じられる海外の空気があったと思います。日本との街並みの違いや食生活の違い等、肌で感じることができ一気に世界が広くなったような気がしました。最終日近くでは凍った湖の上を歩いたり、薪を割ったりとアメリカの自然を感じながら色々なアクティビティができました。
<Q7>最後に・・・今回のGCC参加、あなたにとって一番の収穫は何ですか?
-N.K:英語でのポスター発表が案外、現地の学生に伝わったことです。みなさん真剣に発表を聞いてくれて、リアクションもしてくれました。渡航前はリアクションを伺いながら口頭発表をするなど、自分には絶対無理なことだと思い込んでいましたが、実際にやってみると、自分の実力でも通用する部分があることがわかりました。口頭発表のコツも掴むことができて、英語での研究発表に恐れずに挑める自身がついたと思います。
-T.T:私は自分の研究と今後何をやりたいかについて考える良い機会になりました。自身の研究も面白いですが、他にも様々な分野と目的があると再確認でき、今後どんな分野でどんな研究をしたいか考える良い経験になりました。
-Y.M:積極性の大切さです。GCCは自分から授業を受講したり教授に研究室見学のアポイントを取ったり現地の学生さんと遊びに行く予定を立てたりするなど、主体的に予定をたてられるプログラムでした。自分の積極性次第で充実度が変わることは日本にいても同じだと思うので、今後の生活でも積極性を大切に、充実した日々を過ごせるように意識していこうと思いました。
-F.S:私は日常生活の中での会話方法についての学びと挑戦することの大切さを実感しました。会話、例えばありがとうに対する答え方は思っていたよりも様々な種類がありましたし、店員さんとの会話も教科書で習っている型を意識しすぎてはいけないなと実感しました。学生との会話にはたくさんスラングがあって新鮮で実際に自分なりに使ってもみました。英語圏に身を置くと日本にいるよりも多くの日常表現に触れることができて学びが多かったです。また、何事も恐れてはいけないなと強く実感しました。間違えることを怖がる気持ちはもちろんありましたが、この貴重な機会に怖がっていてはもったいないと感じて、とにかくやってみる!後悔はその後にしようと生活しているうちに考え直しました。やってみれば意外となんとかなるし、やる前から諦めるべきではないと強く思いました。これは海外というより日本で普段生活する際にも心に入れておきたいマインドです。本当にGCCに参加してよかったと思います。
・・・皆さん、今日はありがとうございました。